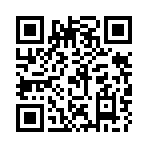2007年08月03日
2007年08月03日
七夕祭り!?
今日から、いよいよ大分の夏の風物詩、七夕祭りです、
そこですこし、調べてみました、「七夕」について、
「七夕の起源」
本来、日本の七夕まつりは、瑞穂国の日本民族とともに、古い時代から、農を主体とした人間生活に密着しながら、複雑な合成過程を経てきたものです。
「七夕」という外来の中国語を、「たなばた」と日本語読みしていることが、いかに古くから「たなばた」の本体があったかを示しています。「たなばた」という日本古来の民俗信仰を母体としながら、その中から盆行事の部分が抽出され、更に中国の技芸上達を願う乞巧奠(きっこうてん)という星祭の行事が合体し、ミックスされたのです。
わが国では、毎年2回、年の始めと7月の満月になる日、すなわち旧暦の正月と7月の15日は、祖霊(それい)を祀る最高潮の日とされていました。正月の七草の日と、7月7日とは15日の祖霊の大祭の準備に入る斉日(いわいび)でした。
旧暦の7月7日頃は、丁度稲が開花期に入るとともに、風水害や病虫害の襲いかかってくる季節でした。秋の豊作を祈るには、ただ一筋に神々にすがる以外に手だてはなかったのです。田の神は、万能の祖霊の変化したものであると信じていました。7日の早朝、人々は禊(みそぎ)をして心身を清め、祖霊を祭るお盆の行事に入ったのでした。これが、農耕文化とともに始まった七夕の起源のようです。
日を定めて帰って来る祖霊(神)に、海山の幸(さち)を供え、新しく織った御衣(ぎょい)を捧げました。この御衣は、選ばれた乙女「棚機女」(たなばたつめ)たちが、沼や川や海の清らかなほとりに特設した機屋(はたや)の「棚機」(たなばた)で、その日のために、心をこめて織り上げたものでした。「たなばた」の語は、この「棚機女」、「棚機」から生じたものであります。 現在、葉竹にさげる紙衣(かみごろも)も、女子の針仕事の上達を願う意味だけでなく、神に捧げる御衣の意味をもつものだそうです。
七夕まつりは江戸時代に入って五節句(人日(じんじつ)、上巳(じょうし)、端午(たんご)、七夕(しちせき)、重陽(ちょうよう))の一つとされてから、全国的に一層盛んに行われるようになりました。
竹飾りも飾られるようになり、始めは五色の願いの糸を垂らすだけだったのが、元禄頃から短冊をさげ、吹流しをつけるようになったということです。
今日は5年生が府内ぱっちんに参加します、5年生!頑張ってね!
夜7時。郵便局前スタートです! みんなで応援しましょう!
そこですこし、調べてみました、「七夕」について、
「七夕の起源」
本来、日本の七夕まつりは、瑞穂国の日本民族とともに、古い時代から、農を主体とした人間生活に密着しながら、複雑な合成過程を経てきたものです。
「七夕」という外来の中国語を、「たなばた」と日本語読みしていることが、いかに古くから「たなばた」の本体があったかを示しています。「たなばた」という日本古来の民俗信仰を母体としながら、その中から盆行事の部分が抽出され、更に中国の技芸上達を願う乞巧奠(きっこうてん)という星祭の行事が合体し、ミックスされたのです。
わが国では、毎年2回、年の始めと7月の満月になる日、すなわち旧暦の正月と7月の15日は、祖霊(それい)を祀る最高潮の日とされていました。正月の七草の日と、7月7日とは15日の祖霊の大祭の準備に入る斉日(いわいび)でした。
旧暦の7月7日頃は、丁度稲が開花期に入るとともに、風水害や病虫害の襲いかかってくる季節でした。秋の豊作を祈るには、ただ一筋に神々にすがる以外に手だてはなかったのです。田の神は、万能の祖霊の変化したものであると信じていました。7日の早朝、人々は禊(みそぎ)をして心身を清め、祖霊を祭るお盆の行事に入ったのでした。これが、農耕文化とともに始まった七夕の起源のようです。
日を定めて帰って来る祖霊(神)に、海山の幸(さち)を供え、新しく織った御衣(ぎょい)を捧げました。この御衣は、選ばれた乙女「棚機女」(たなばたつめ)たちが、沼や川や海の清らかなほとりに特設した機屋(はたや)の「棚機」(たなばた)で、その日のために、心をこめて織り上げたものでした。「たなばた」の語は、この「棚機女」、「棚機」から生じたものであります。 現在、葉竹にさげる紙衣(かみごろも)も、女子の針仕事の上達を願う意味だけでなく、神に捧げる御衣の意味をもつものだそうです。
七夕まつりは江戸時代に入って五節句(人日(じんじつ)、上巳(じょうし)、端午(たんご)、七夕(しちせき)、重陽(ちょうよう))の一つとされてから、全国的に一層盛んに行われるようになりました。
竹飾りも飾られるようになり、始めは五色の願いの糸を垂らすだけだったのが、元禄頃から短冊をさげ、吹流しをつけるようになったということです。
今日は5年生が府内ぱっちんに参加します、5年生!頑張ってね!
夜7時。郵便局前スタートです! みんなで応援しましょう!
Posted by danoharuman at
17:32
│Comments(0)