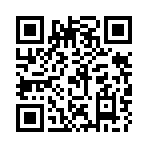2007年08月04日
ねぶた祭と府内ぱっちん
昨夜の府内ぱっちん、盛り上がりましたね、
5年生もがんばって踊りましたよ、ご覧になりました?
来年も頑張ろう!
今日は、府内ぱっちんの原型と思われる、弘前ねぶた祭りの起源についてを調べてみました。
「弘前ねぶた祭りの起源」
津軽の夏の夜を焦がす弘前ねぷたまつりは、三国志や水滸伝などを題材にした勇壮で色鮮やかな武者絵が描かれた扇ねぷたや、組ねぷた大小合わせて約60台が、ヤーヤドーの掛け声と共に市内を練り歩きます。
ねぷたの起源には、平安時代初期、征夷大将軍・坂上田村麻呂が蝦夷征伐の時に創造したという伝説や、文禄2年(1593年)7月、初代藩主為信公により、京都で創始という伝承もありますが、江戸時代元禄期の後半(18世紀初頭以降)、七夕祭りの松明流しや精霊流し、眠り流し、盆灯籠などから変化して、発展してきたというのが定説となっています。
語源は、眠り流し→ねむた流し→ねむた→ねぷた(ねぶた)と変わっていったものといわれて、暑さの厳しい、しかも農作業の激しい夏期に襲ってくる睡魔(ねむたい)を追い払うための行事で村中一団となって、様々な災い、邪悪を水に流して村の外に送り出すためともいわれています。
ところで、みなさん「府内ぱっちん」の由来、御存じですか?
「府内」とは大分市の古称、「パッチン」は「メンコ」の大分方言です。
12年前、大分大分商工会議所青年部の皆さんが、町起こしの一環として、電照をしつらえた大ミコシを大分七夕祭りの市民ミコシの 一台として登場させ、 当時の市長が思わず「パッチン」のようだと行った事が命名となったということらしいです。
府内ぱっちんの歴史はまだ浅いですがその分、これから1年1年、私たちみんなで歴史を築いていきましょう、お祭りは継続こそ、バリューアップにつながるのですから、
実行委員の皆様、お疲れさまです、来年も更なる、せいやー! の掛け声をよろしくお願いいたします。

だのはる広場管理人danoharuman
5年生もがんばって踊りましたよ、ご覧になりました?
来年も頑張ろう!
今日は、府内ぱっちんの原型と思われる、弘前ねぶた祭りの起源についてを調べてみました。
「弘前ねぶた祭りの起源」
津軽の夏の夜を焦がす弘前ねぷたまつりは、三国志や水滸伝などを題材にした勇壮で色鮮やかな武者絵が描かれた扇ねぷたや、組ねぷた大小合わせて約60台が、ヤーヤドーの掛け声と共に市内を練り歩きます。
ねぷたの起源には、平安時代初期、征夷大将軍・坂上田村麻呂が蝦夷征伐の時に創造したという伝説や、文禄2年(1593年)7月、初代藩主為信公により、京都で創始という伝承もありますが、江戸時代元禄期の後半(18世紀初頭以降)、七夕祭りの松明流しや精霊流し、眠り流し、盆灯籠などから変化して、発展してきたというのが定説となっています。
語源は、眠り流し→ねむた流し→ねむた→ねぷた(ねぶた)と変わっていったものといわれて、暑さの厳しい、しかも農作業の激しい夏期に襲ってくる睡魔(ねむたい)を追い払うための行事で村中一団となって、様々な災い、邪悪を水に流して村の外に送り出すためともいわれています。
ところで、みなさん「府内ぱっちん」の由来、御存じですか?
「府内」とは大分市の古称、「パッチン」は「メンコ」の大分方言です。
12年前、大分大分商工会議所青年部の皆さんが、町起こしの一環として、電照をしつらえた大ミコシを大分七夕祭りの市民ミコシの 一台として登場させ、 当時の市長が思わず「パッチン」のようだと行った事が命名となったということらしいです。
府内ぱっちんの歴史はまだ浅いですがその分、これから1年1年、私たちみんなで歴史を築いていきましょう、お祭りは継続こそ、バリューアップにつながるのですから、
実行委員の皆様、お疲れさまです、来年も更なる、せいやー! の掛け声をよろしくお願いいたします。

だのはる広場管理人danoharuman
Posted by danoharuman at 12:24│Comments(2)
この記事へのコメント
わたしは、おどったものです。思ったより、きついですよー。こんど、おどってみてくださいねー。
Posted by at 2007年08月30日 18:33
コメント有難うございます、
画像のチームで踊ったんですか?
僕も来年はチャンスがあれば参加してみたいですね、そのときはよろしくです。
画像のチームで踊ったんですか?
僕も来年はチャンスがあれば参加してみたいですね、そのときはよろしくです。
Posted by danoharuman at 2007年08月31日 22:40