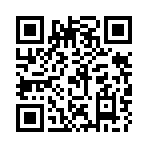2007年07月23日
養老先生のお話
数年前、NHKの番組で脳の特集があったのを偶然見ました。
このなかで養老先生のコメント、とても共感を憶えました、当時の自分の考えをすべて包括してくれる理論でした。特に虫取りのことなどはほんと、有り難く受け取っています。
少年時代の虫取りは脳によい刺激を与えてくれたり、人間が本来は持っていたある感覚を覚醒させてくれるようです。我が虫取り一家、まちがえてなかった。という事にしています。
現時点で公開されている先生の以前の講演内容要旨を下記に転記してみたので興味のあるかた是非、お目通し下さい。
「部屋を掃除した結果の
地球温暖化に気づいているか」
多様な価値観があるのはいいんですけれども、強制すると具合が悪くて、これは我々の意識の持っている癖なんです。
例えば、部屋に無秩序にゴミが溜まります。そのゴミを掃除機で吸い取ると、床の上がきれいになって秩序が高くなります。すると皆さんはその部屋の分だけ、世界の秩序が高くなったという考え方をしていませんか。
それが間違いです。ちょっと視野を広げると、掃除をする前よりも掃除機は何倍も汚れ、部屋の無秩序は掃除機の中に引っ越しただけ。
満杯になった掃除機のゴミを捨て、焼却場へ行って燃すと、高分子が低分子に変わって熱を発生し、すなわち最終的には地球の温暖化になって終わります。それを気がついてないでしょう。自分のところをきれいにすれば、世界はそれだけきれいになるというのが、今の人の暗黙の信念ですよ。
これを物理学では、一方に秩序が立つと、他方に同じ量の無秩序が発生するといい、熱力学ではエントロピーが増大するといいます。これがなかなかわかっていただけないことと、現代社会が生きづらく重苦しくなっていることと、非常に深く関係していると思います。
それを示す好例が、最近の田舎に猿が出る、鹿や熊が出る問題。これも日本中の犬を紐でつないで、飼い主のいない野犬を全部狩り尽すというルールを引いたからです。犬がいたら猿は出てきません。犬をつなぎ、野犬を狩るのはよいことだと考え、その結果を背負ったのは過疎地の農家です。
きちんとすることはいいことだって、今や完全な常識になりつつあります。日本政府はここ10年間で300法令を作ったそうです。ルールを作れば、世の中はうまくいくと信じ込んでいる証拠ですよね。残念ながら、根本のところに大穴があいているんですが。
もう一つ例えれば、意識は図書館です。目が覚めると、一日に何が起こるか決まっていませんから、客が勝手に本を出して帰ってしまう。本が出尽くして図書館として使えなくなった時、「眠くてしょうがない」といい、図書館を閉めて眠ります。閉めると、司書が出てきて、机の上に出ている本を元の位置に戻します。机がきれいに空けば、目を覚まして図書館を開けます。だから、本を出すのに必要なエネルギーは、片付けるのにも同じだけのエネルギーが必要なんです。眠らずにいると酷い時は、脳が壊れます。
自分自身の中に出たゴミは、寝ることで片付きますが、問題は頭で考えた秩序を外の世界に出していくと、別のところに気がつかないゴミがたまることです。田舎に出てきた猿や熊のように、都会の人は気がつきません。今、環境問題とか公害問題といわれる根本には、これがあります。
視点は一人一人違って当然
「人を見る目」を持つこと
で、多様な価値観の話です。いろいろな価値観には、意識に二つの面があることをご理解してほしい。感覚でとらえた「違う」世界と、概念でとらえた「同じ」世界です。この会場にいる方は、感覚で見ると全部違う人なんです。でも、「人」っていう概念でいうと、全部同じになっちゃう。「同じ」と「違う」は、相互に補完的です。同じ人間という意味では同じだけど、他人と違うといえば違う。お互いに補い合う。
例えば、日本人の一人一人に「猫」といってもらうと、その音は全部違います。文字を百回書いても、百回とも必ず違う字を書いてしまう。つまり、同じものはない。それは小さな違いといいますが、じゃあ、どこから大きな違いになるんでしょう。
我々は、同じという能力を持ったために、言葉が使えるようになったんです。動物はこの能力がほとんどありませんから、同じとは考えない。動物の感覚の世界では、すべてが違う。価値観の多様性とは、このことです。
もし、会場にテレビカメラがあったとして、私の姿を映しているとすれば、その同じ位置からは誰も見ることができない。同じというのは、同じ価値でしょう。視点は一人一人全部違うのを、テレビ局の個人が映した画像を、公平・客観・中立だといって毎日流し、抗議の手紙もないんですから、そういった違いは今の世界では無視されていると考えざるをえない。その結果、一般市民だとかただのサラリーマンだとか普通の人と同じにくくりますが、動物の世界ではくくりません。
10年以上前のあるテレビ局の実験で、三日間冷蔵庫に入れたサンマと、きょう買ってきたサンマを猫に与えると、猫は三日前のサンマを絶対食べない。冷蔵庫に入れておいても、不飽和脂肪酸をたくさん含んで酸化したサンマは、匂いが悪いので食べません。人間は、きょう買ったサンマを奥さんが食べて、三日前のを旦那が食べて、同じサンマだと思っている。それが同じっていう能力なんです。
この能力がないと社会はできないんですが、すべては違うという感覚の世界を、現代社会は置いてきてしまった。
人一人一人は全部かけがえのない違う人であり、その違いを絶えず重ねていくことが年をとるということですが、今の人はまったくわからなくなっているんですよ。
昔の人は、個性なんてことをいいません。「人を見る目」といいました。個性というものが皆さんの中にあると考えるのは、「猫」の正しい発音、正しい文字があるという考えと同じでしょう。そうじゃなくて、ロビンソン・クルーソーが毎朝海岸に出て、「俺の個性は」って海に怒鳴っても、何の意味もないっておわかりになりませんか? 人が大勢いるから個性が意味を持ってくるんで、それを見分ける目が、人を見る目でしょう。昔は年寄りが、人を見る目を持っていたのです。お前はああしろ、これしちゃだめだ、ちょっとやりすぎだよとか、注意してくれる師匠がいたはずです。
個性という前に、人がどう見るか、人をどう見るかということ。これ、実は個性と同じことなんです。年寄りのやらなきゃいけないことは、こういうことだったんですね。
若い人が、若い人らしくなくならないように。
以上です。
是非、最新の講演を聞きたいものです。
養老 孟司 さん
(ようろう たけし)
東京大学名誉教授/日本ペンクラブ会員
1937年神奈川県生まれ。東大医学部卒業後、解剖学を専攻し東大教授に。退官後、北里大教授に就任。形態・言語・数学・時間など、様々な事柄を脳の働きの観点から分析、ヒトの精神活動や脳内過程の解明をめざす。著書も多く、「バカの壁」はベストセラーに。
このなかで養老先生のコメント、とても共感を憶えました、当時の自分の考えをすべて包括してくれる理論でした。特に虫取りのことなどはほんと、有り難く受け取っています。
少年時代の虫取りは脳によい刺激を与えてくれたり、人間が本来は持っていたある感覚を覚醒させてくれるようです。我が虫取り一家、まちがえてなかった。という事にしています。
現時点で公開されている先生の以前の講演内容要旨を下記に転記してみたので興味のあるかた是非、お目通し下さい。
「部屋を掃除した結果の
地球温暖化に気づいているか」
多様な価値観があるのはいいんですけれども、強制すると具合が悪くて、これは我々の意識の持っている癖なんです。
例えば、部屋に無秩序にゴミが溜まります。そのゴミを掃除機で吸い取ると、床の上がきれいになって秩序が高くなります。すると皆さんはその部屋の分だけ、世界の秩序が高くなったという考え方をしていませんか。
それが間違いです。ちょっと視野を広げると、掃除をする前よりも掃除機は何倍も汚れ、部屋の無秩序は掃除機の中に引っ越しただけ。
満杯になった掃除機のゴミを捨て、焼却場へ行って燃すと、高分子が低分子に変わって熱を発生し、すなわち最終的には地球の温暖化になって終わります。それを気がついてないでしょう。自分のところをきれいにすれば、世界はそれだけきれいになるというのが、今の人の暗黙の信念ですよ。
これを物理学では、一方に秩序が立つと、他方に同じ量の無秩序が発生するといい、熱力学ではエントロピーが増大するといいます。これがなかなかわかっていただけないことと、現代社会が生きづらく重苦しくなっていることと、非常に深く関係していると思います。
それを示す好例が、最近の田舎に猿が出る、鹿や熊が出る問題。これも日本中の犬を紐でつないで、飼い主のいない野犬を全部狩り尽すというルールを引いたからです。犬がいたら猿は出てきません。犬をつなぎ、野犬を狩るのはよいことだと考え、その結果を背負ったのは過疎地の農家です。
きちんとすることはいいことだって、今や完全な常識になりつつあります。日本政府はここ10年間で300法令を作ったそうです。ルールを作れば、世の中はうまくいくと信じ込んでいる証拠ですよね。残念ながら、根本のところに大穴があいているんですが。
もう一つ例えれば、意識は図書館です。目が覚めると、一日に何が起こるか決まっていませんから、客が勝手に本を出して帰ってしまう。本が出尽くして図書館として使えなくなった時、「眠くてしょうがない」といい、図書館を閉めて眠ります。閉めると、司書が出てきて、机の上に出ている本を元の位置に戻します。机がきれいに空けば、目を覚まして図書館を開けます。だから、本を出すのに必要なエネルギーは、片付けるのにも同じだけのエネルギーが必要なんです。眠らずにいると酷い時は、脳が壊れます。
自分自身の中に出たゴミは、寝ることで片付きますが、問題は頭で考えた秩序を外の世界に出していくと、別のところに気がつかないゴミがたまることです。田舎に出てきた猿や熊のように、都会の人は気がつきません。今、環境問題とか公害問題といわれる根本には、これがあります。
視点は一人一人違って当然
「人を見る目」を持つこと
で、多様な価値観の話です。いろいろな価値観には、意識に二つの面があることをご理解してほしい。感覚でとらえた「違う」世界と、概念でとらえた「同じ」世界です。この会場にいる方は、感覚で見ると全部違う人なんです。でも、「人」っていう概念でいうと、全部同じになっちゃう。「同じ」と「違う」は、相互に補完的です。同じ人間という意味では同じだけど、他人と違うといえば違う。お互いに補い合う。
例えば、日本人の一人一人に「猫」といってもらうと、その音は全部違います。文字を百回書いても、百回とも必ず違う字を書いてしまう。つまり、同じものはない。それは小さな違いといいますが、じゃあ、どこから大きな違いになるんでしょう。
我々は、同じという能力を持ったために、言葉が使えるようになったんです。動物はこの能力がほとんどありませんから、同じとは考えない。動物の感覚の世界では、すべてが違う。価値観の多様性とは、このことです。
もし、会場にテレビカメラがあったとして、私の姿を映しているとすれば、その同じ位置からは誰も見ることができない。同じというのは、同じ価値でしょう。視点は一人一人全部違うのを、テレビ局の個人が映した画像を、公平・客観・中立だといって毎日流し、抗議の手紙もないんですから、そういった違いは今の世界では無視されていると考えざるをえない。その結果、一般市民だとかただのサラリーマンだとか普通の人と同じにくくりますが、動物の世界ではくくりません。
10年以上前のあるテレビ局の実験で、三日間冷蔵庫に入れたサンマと、きょう買ってきたサンマを猫に与えると、猫は三日前のサンマを絶対食べない。冷蔵庫に入れておいても、不飽和脂肪酸をたくさん含んで酸化したサンマは、匂いが悪いので食べません。人間は、きょう買ったサンマを奥さんが食べて、三日前のを旦那が食べて、同じサンマだと思っている。それが同じっていう能力なんです。
この能力がないと社会はできないんですが、すべては違うという感覚の世界を、現代社会は置いてきてしまった。
人一人一人は全部かけがえのない違う人であり、その違いを絶えず重ねていくことが年をとるということですが、今の人はまったくわからなくなっているんですよ。
昔の人は、個性なんてことをいいません。「人を見る目」といいました。個性というものが皆さんの中にあると考えるのは、「猫」の正しい発音、正しい文字があるという考えと同じでしょう。そうじゃなくて、ロビンソン・クルーソーが毎朝海岸に出て、「俺の個性は」って海に怒鳴っても、何の意味もないっておわかりになりませんか? 人が大勢いるから個性が意味を持ってくるんで、それを見分ける目が、人を見る目でしょう。昔は年寄りが、人を見る目を持っていたのです。お前はああしろ、これしちゃだめだ、ちょっとやりすぎだよとか、注意してくれる師匠がいたはずです。
個性という前に、人がどう見るか、人をどう見るかということ。これ、実は個性と同じことなんです。年寄りのやらなきゃいけないことは、こういうことだったんですね。
若い人が、若い人らしくなくならないように。
以上です。
是非、最新の講演を聞きたいものです。
養老 孟司 さん
(ようろう たけし)
東京大学名誉教授/日本ペンクラブ会員
1937年神奈川県生まれ。東大医学部卒業後、解剖学を専攻し東大教授に。退官後、北里大教授に就任。形態・言語・数学・時間など、様々な事柄を脳の働きの観点から分析、ヒトの精神活動や脳内過程の解明をめざす。著書も多く、「バカの壁」はベストセラーに。